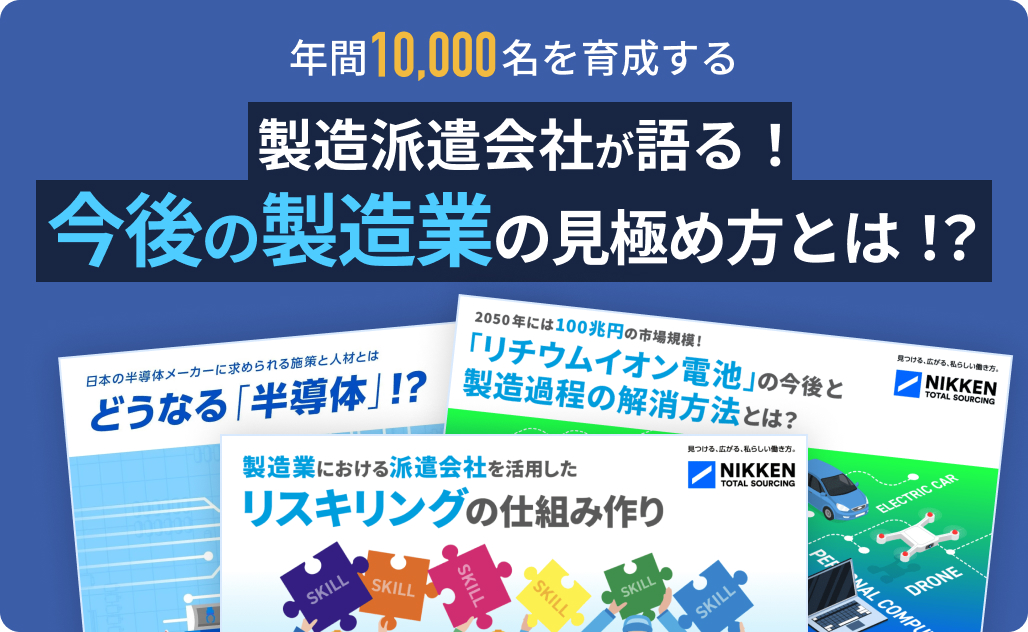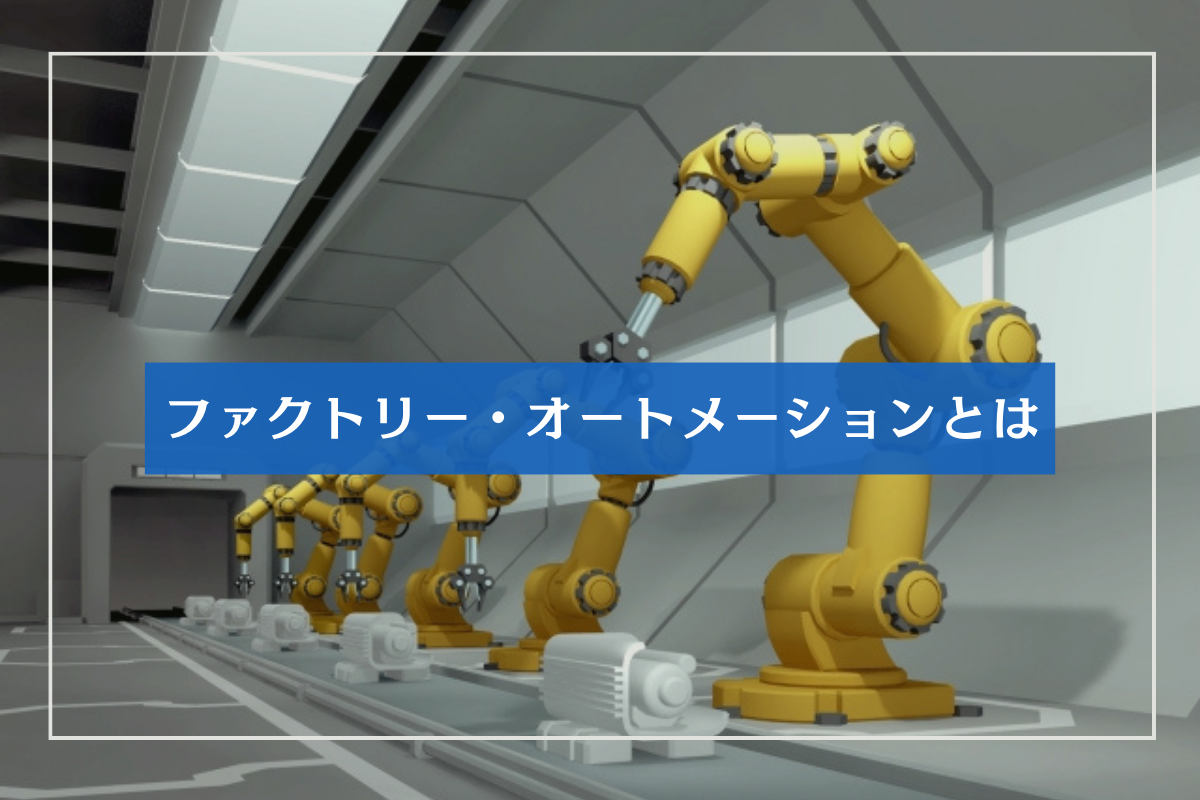
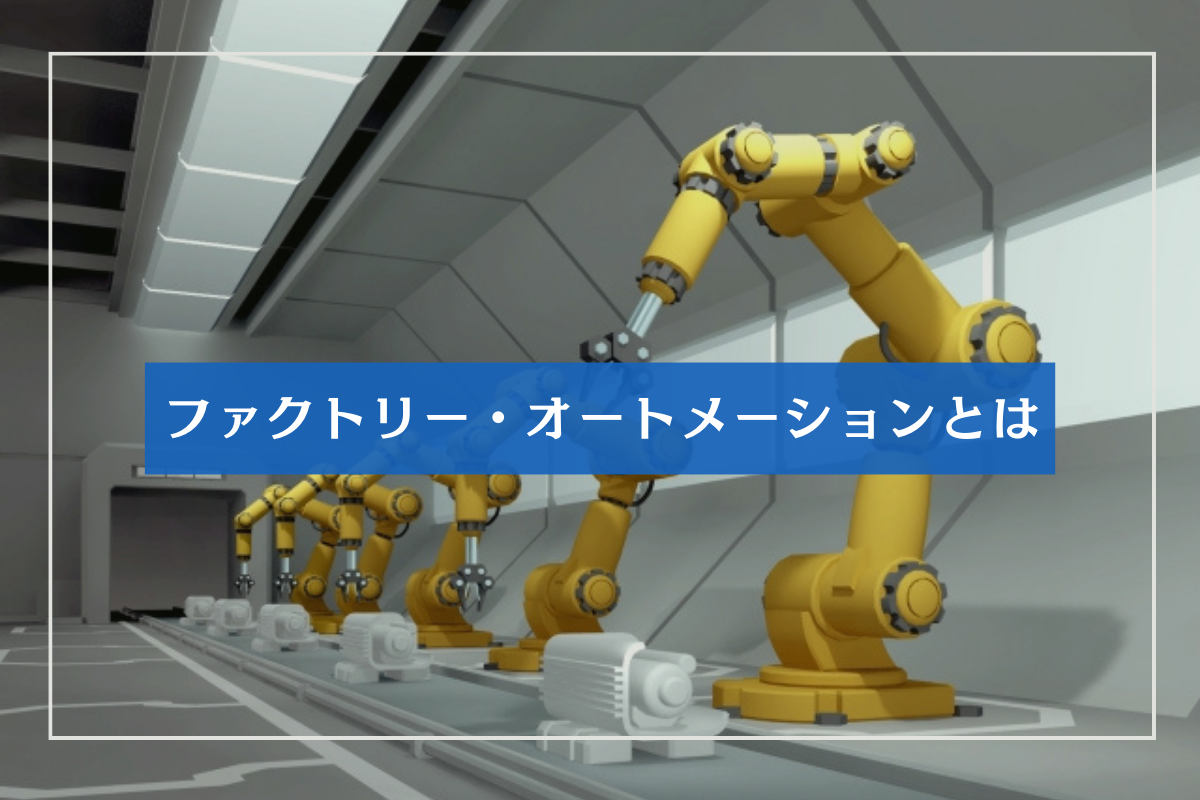
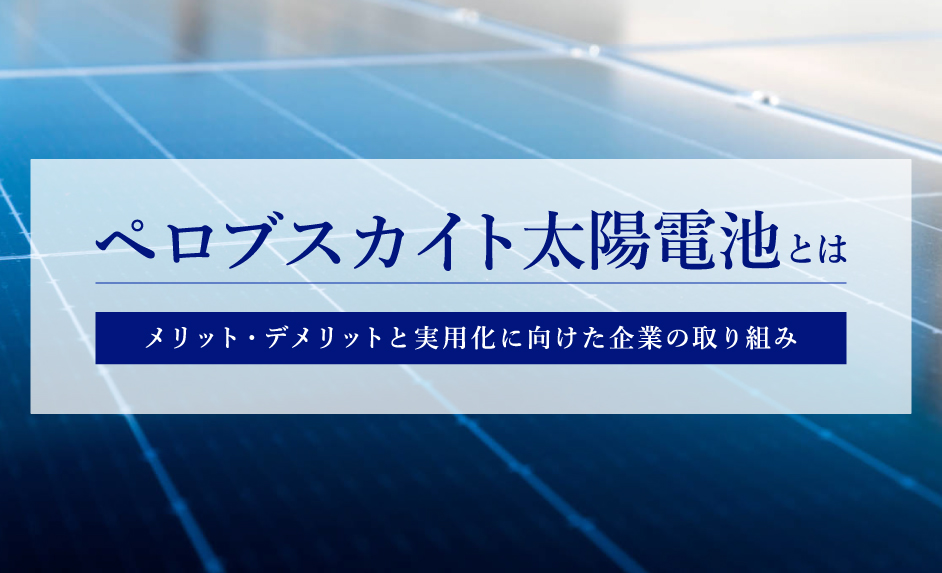
脱炭素社会の実現に向けて、太陽光発電があらためて注目されているいま、次世代太陽電池として期待されているのがペロブスカイト太陽電池(ペロブスカイト型太陽電池)です。
これまでも新技術を用いた太陽電池はいくつか登場したものの、現在の主力となっているシリコン太陽電池にとって代わるには至りませんでした。しかし、従来のシリコン太陽電池が直面するコストの問題や設置場所の制限といった難題を解決するポテンシャルがあり、価格面の優位性も備えるペロブスカイト太陽電池への期待値は大いに高まっています。
耐久性や不安定性などのデメリットも指摘されているものの、ペロブスカイト太陽電池はシートに印刷して折り曲げることができるなど、いままでの常識を大きく覆す太陽電池であることは間違いありません。
お役立ち資料はこちら

ペロブスカイト太陽電池とは、太陽の光エネルギーを電気に変換する結晶構造を持つ、ペロブスカイトという材料を用いた「ペロブスカイト半導体」を使った太陽電池です。
| 主な材料 | ペロブスカイト半導体 |
| 発明者 | 桐蔭横浜大学 宮坂力教授 |
| 関連特許 | 積水化学工業、富士フイルムホールディングス等 |
ペロブスカイトはロシアのウラル山脈で発見された鉱物ですが、同様の結晶構造を持つ素材は、一般的な化学物質から合成してつくることが可能です。理論上では、ペロブスカイトの結晶構造をつくる化学物質の組み合わせや構成比は、600種類以上あるとされています。
なお、2009年に太陽電池の材料としてペロブスカイトを発見した発明者は日本の桐蔭横浜大学の宮坂力教授であり、ペロブスカイト太陽電池は日本の研究開発によって生まれたものです。
宮坂氏はノーベル賞の有力候補ともいわれており、大学発ベンチャーで国内特許も取得。積水化学工業や富士フイルムホールディングスなど国内フィルム大手企業もペロブスカイト太陽電池のモジュール化に関する特許を積極的に出願しています。
※モジュール:太陽光発電パネル一枚を指す呼称。パネルとも呼ばれる
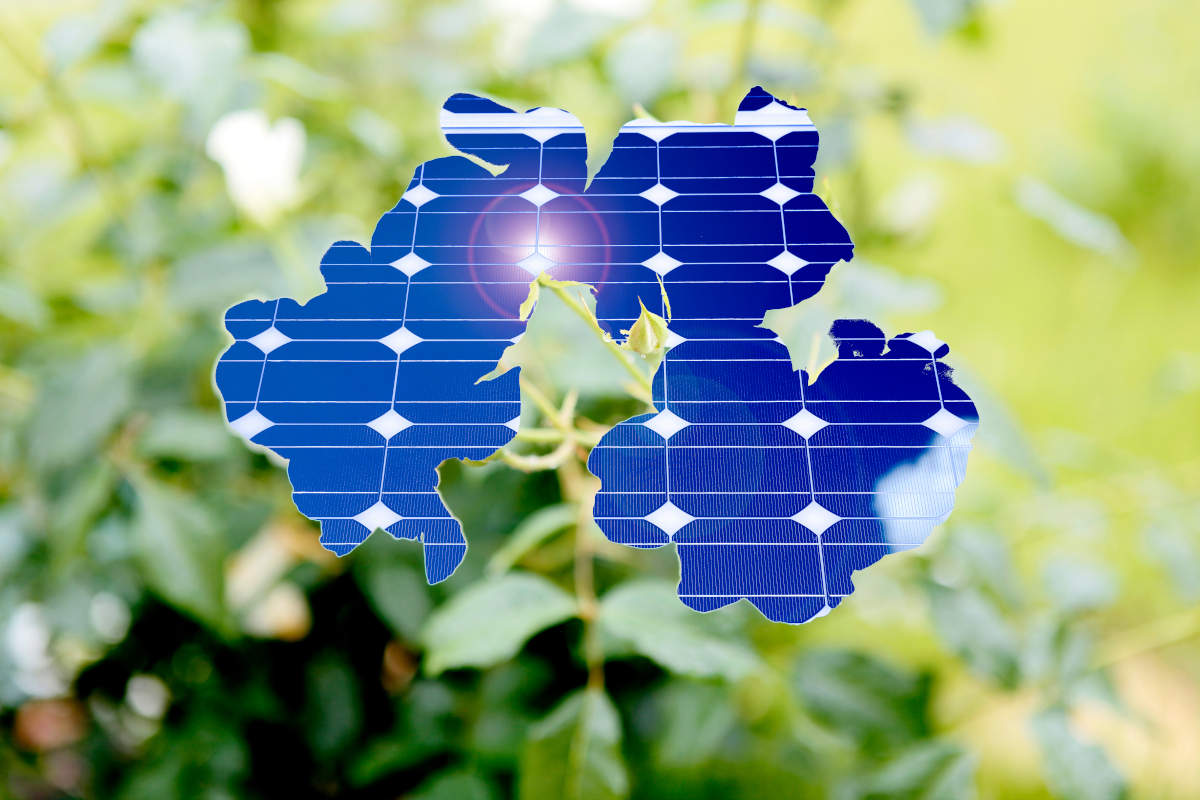
ペロブスカイト太陽電池は、次に挙げる利点やメリットから、シリコン太陽電池に代わる次世代太陽電池として注目されています。
現在、広く普及しているシリコン太陽電池は、価格の高さが今後のさらなる普及のネックとなっています。
シリコンを用いるには多くの製造工程が必要であり、高温プロセスもあるため、電力消費量も大きくなります。一方、ペロブスカイトは溶解処理による簡素化された製造工程で済むため、コストの高い生産設備を必要とせず、かつ低温プロセスのみで製造できるため、電気消費量も抑えられます。
また、ペロブスカイトを半導体の材料に薄膜として用いるため、シリコンを使う場合と比較して20分の1程度の材料で済むとされています。
結果、実用化にあたってペロブスカイト電池の製造コストは、シリコン太陽電池の5分の1から3分の1程度になると見込まれています。
ペロブスカイト太陽電池の主原料となる「ヨウ素」は、日本国内で自給できます。
米中の対立やロシアのウクライナ侵略などによりサプライチェーンの強靭化が求められる今、原材料の供給を巡る問題が起こりにくいことは大きなメリットです。
同じくレアメタルフリーを実現するナトリウムイオン電池や、生物資源を燃料とするバイオマス発電と同様に、 ペロブスカイト太陽電池はエコかつ高コストパフォーマンスである観点からも注目されています。
シリコン太陽電池は薄くすると、太陽の光エネルギーの吸収効率が低下します。そのため薄くすることは困難であり、厚みがあって折ることもできないため、耐荷重の問題からも設置場所は制限されていました。
一方、ペロブスカイト太陽電池は太陽の光エネルギーの吸収係数が大きいことから、薄くしても高い変換効率を維持できます。さらに特別な加工も必要とせず、印刷と同様の付加的成膜技術で製造できるため、低エネルギー、低コストでの製造が可能です。実際にインクジェット印刷に近い製法もすでに展開されています。
こうした特徴から、ペロブスカイト太陽電池はソーラーパネルのような長方形の形状だけではなく、軽く薄く柔らかいフレキシブルな形状にできます。例えば、建物の壁、あるいは車体、衣服、ウェアラブルデバイスといった曲面に設置して、太陽の光のエネルギーを活用して発電を行えるなど、これまでの難題であった設置場所の制限が緩くなることは大きなメリットです。
価格面、製造面、運用面で優れるペロブスカイト太陽電池ですが、実用化に向けては課題も残されています。
モジュールの大面積化や変換効率の向上については、現在も鋭意開発が進んでおり、上述の通り大手フィルムメーカーも特許を積極的に出願しています。
一般的なシリコン太陽電池では、太陽の光エネルギーから電気への変換効率が20%以上。なかには25%を超えるもののあります。それにはまだまだ及ばないものの、変換効率が15%を超えるペロブスカイト太陽電池も東芝によって開発されています。
そして、実用化に向けて最大の課題となるのは、ペロブスカイトの不安定性です。
ペロブスカイトは酸素や水分といった外的影響を受けやすく、加熱劣化による内的不安定性もあります。こうした特性から、結晶内で結合に支障をきたしてしまうと、電子が効率よく移動できなくなり、太陽の光エネルギーから電気への変換効率が低下する可能性が否めません。
こうした課題が解決できなければ、ペロブスカイト太陽電池の安定稼働は困難になるため、従来のシリコン太陽電池から切り替わるのはまだまだ難しいとみられています。
また、ペロブスカイト化合物に鉛を使用していることへの懸念もあります。ペロブスカイト太陽電池に使用されている鉛は、鉛電池やカドミウム電池と比較すると少量ですが、周辺環境への溶出が不安視されているためです。
鉛と同等の変換効率となる材料を見つける、あるいは外部に溶出しないような完全な封じ込めを行うといった対策が求められています。
ペロブスカイト太陽電池の特徴には、次の点が挙げられます。
太陽電池は半導体の材料による種類があり、現在、主流のシリコン太陽電池は約95%のシェアを占めているとされています。
しかし、シリコン太陽電池は重く、設置場所にも制限があります。たとえば、ビルの側面や耐荷重の小さい屋根では、どんなに日当たりがよくてもシリコン太陽電池を設置することはできません。また、製造工程で高温となるプロセスがあるため、電力消費量が大きいことも課題でした。
これに対して、ペロブスカイト太陽電池は、シートに印刷するなど塗布によって簡単に製造可能点が大きな特徴です。折り曲げられる柔軟性のある形状にすることや軽量化も実現でき、設置場所もフレキシブルに対応できます。
さらに、シリコン太陽電池よりも価格が安くなるとされていることからも、次世代太陽電池として期待されているのです。
一般的な太陽電池に共通した仕組みとして、太陽の光エネルギーを受けると、半導体の材料の電子のエネルギーが高まり、導電性の電極に流れ込んで電流が発生します。この半導体の材料にシリコンを使ったのがシリコン太陽電池であり、ペロブスカイト太陽電池は鉛のペロブスカイト結晶構造に太陽の光エネルギーをあてる仕組みです。
ペロブスカイト太陽電池は、太陽の光エネルギーから電気への変換効率が飛躍的に向上してきています。シリコン太陽電池と同程度に迫る変換効率を実現したとする研究結果も打ち出されているほど、研究開発が進んでいるのです。
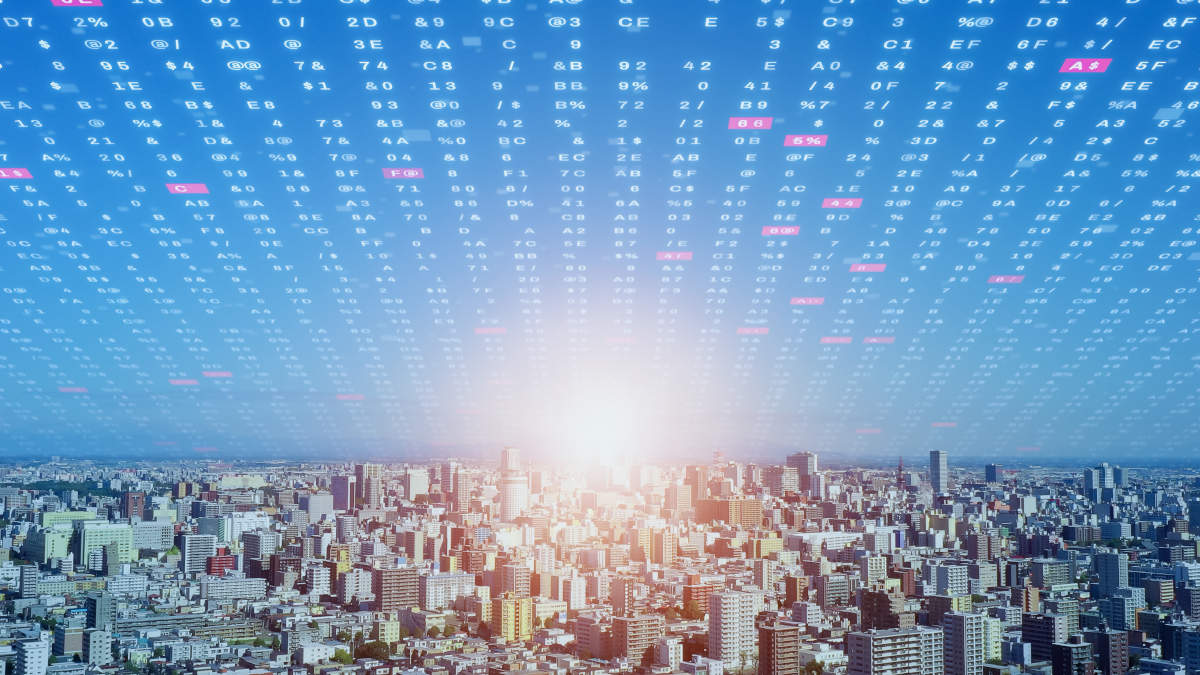
ペロブスカイト太陽電池の実用化に向けてはクリアしなければならない課題もありますが、すでに多くの企業が研究開発に取り組んでいます。
新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)はペロブスカイト太陽電池の実用化を推進するため、200億円を投じた開発支援を行っており、東芝などの6つの事業が採択されました。ペロブスカイト太陽電池の実用化に向けた、主な企業の取り組みをみていきましょう。
東芝では、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託事業の「太陽光発電主力電源化推進技術開発」の一環として、フィルム型のペロブスカイト太陽電池の開発を進めています。
2021年9月には703平方センチメートルのモジュールで、太陽の光エネルギーの電気への変換効率15.1%を実現。フィルム型のペロブスカイト太陽電池として世界最高のエネルギー変換効率を達成しています。
2018年の段階では変換効率は14.1%であったため、これは1%の向上の実現となります。2018年6月に開発したモジュールからさらに進化を遂げ、ペロブスカイト太陽電池の実用化に、また一歩近づいた形です。
東芝では今後の目標として、2025年までにモジュールの900平方センチメートルへの大面積化を図るとともに、変換効率は20%以上、発電コストは1kWあたり20円以下のペロブスカイト太陽電池の実用化を目指しています。
自動車部品のサプライヤーとして世界に知られるアイシンも、ペロブスカイト型太陽電池関連事業に本格的に参入。20%以上の変換効率を目標とし2025年の実証実験を目指し、研究開発を進めています。
アイシンが注力しているのは、ペロブスカイト型太陽電池の素材の塗布技術の向上です。住宅の壁などのほか、ウェアラブルデバイスやハンディ扇風機、自動車などへの搭載も念頭に、スプレー工法技術の実用化を目指しています。この塗布技術が確立されれば、機器を利用しながらの発電や充電も可能となるでしょう。
積水化学工業では、ペロブスカイト太陽電池を脱炭素社会実現の鍵になる技術のひとつに位置付け、2025年の事業化を目指しています。2021年7月には14.3%の変換効率を達成。今後は15%を目指す方針です。
さらに2023年4月からは、国内初となるフィルム型ペロブスカイト太陽電池を建物の外壁に設置する実証実験を開始。課題抽出を経て、都心部の既存建築物への設置を目指します。
リコーは宇宙航空研究開発機構(JAXA)とペロブスカイト太陽電池の共同開発を進めています。
これまでも人工衛星には太陽電池が搭載されてきましたが、ペロブスカイト太陽電池の軽量でコストを抑えられる特性は、人工衛星の開発においても大きなメリットになります。人工衛星の軽量化が図れれば、打ち上げコストの削減にも寄与するでしょう。また、放射線による劣化が少なく、光量が少なくても発電が可能であり、変換効率が高いことからも、宇宙空間での利用に向いているとされています。
そこで、リコーとJAXAは宇宙での利用も可能な耐久性が高く軽量化されたペロブスカイト太陽電池の開発を行っており、成層圏での実証実験でデータ収集を行った結果、暗い宇宙空間で高い発電効率を維持することに成功しています。
電子機器や情報通信機器を手掛けるホシデンは、滋賀県にある関連会社のホシデンエフディの既存のタッチパネルの製造ラインが転用できることから、ペロブスカイト太陽電池の事業に進出しました。ペロブスカイト太陽電池は軽量化が可能なため、モバイル機器やIoT機器への搭載への応用が期待できることが、開発に踏み切った理由のひとつです。
ホシデンでは2021年にサンプル生産をスタートし、2022年に量産用の生産設備の導入を行い、2023年からは量産を前提としたサンプル開発に着手。さらに2024年度には量産化の達成を目指しています。
ペロブスカイト太陽電池の技術は日本発であり、開発において世界をリードする立場にあります。しかし欧米・中国などでも開発が急速に進展しており、競争が加速している状態といえるでしょう。
| 中国 |
・2015年頃からスタートアップ企業が複数設立。企業や大学が自国内の特許取得を進めており、研究開発競争は激化 ・DazhengやGCLPerovskiteなどが量産に向けた動き |
| イギリス | ・オックスフォードPV(オックスフォード大学発スタートアップ)は、タンデム型太陽電池技術の商品化・量産化・製造プロセスの開発に注力、2025年前後の大量生産を目指す |
| ポーランド | ・サウレ・テクノロジーズが、屋内向けの電子商品タグ等の2023年内の商用化を計画、壁面実証の取組開始 |
参考:次世代型太陽電池の早期社会実装に向けた追加的取組について
世界シェアを広げるにあたり必須となる「補助金」ですが、政府は2023年に予算を498億円から648億円に引き上げ、社会実装の目標も2030年から2025年に前倒ししています。
日本には、かつて太陽光では政府の補助を受けた中国との価格競争に敗れ、シェアの大半を奪われた過去があります。今後のシェア奪還に向けて政府の補助は言うまでもなく重要となりますが、併せて民間企業が事業投資に踏み切るための「需要の創出」と「導入促進」も急がれます。
ゲームチェンジには、民間を巻き込んだ大規模な目標と施策が必要です。
ペロブスカイト太陽電池は従来のシリコン太陽電池の製造における電力消費量や価格の高さ、設置場所の制限といった課題の解決が期待されている次世代太陽電池です。これまでは耐荷重の問題から設置が難しかった場所にも設置可能であり、ビルの側面など新たな設置場所も生まれることから、実用化によって太陽光発電のさらなる普及に貢献すると見込まれているのです。
宮坂教授がペロブスカイト太陽電池を開発したように、電池に関する研究開発分野は日本のお家芸でもあります。実用化・量産化に向けて日本が先行している全個体電池とならび、世界を牽引する技術開発が期待されます。
また、ペロブスカイト太陽電池によって設置箇所が大幅に増えることは、太陽光発電システムの新たな需要を掘り起こすトリガーにもなります。日本発のペロブスカイト太陽電池が、数年後にはビルの屋上や側面に設置されている。それは当たり前の光景になっているかもしれません。
日研トータルソーシングでは、製造業の設備保全サービスにおける人材活用を、トータルでサポートしています。充実した教育カリキュラムの導入によって、高い専門スキルを持った人材育成にも力を入れており、保全研修の外販実績も豊富にございます。
これら弊社独自の取り組みをサービス資料としてまとめております。人材教育、外部委託などをご検討されている企業の皆様、ぜひ御覧ください。
お役立ち資料はこちら
半導体・電池業界の研修実績年間10,000名を超える派遣会社が「今後の製造現場を左右する情報」をまとめた資料セットを作成しました。